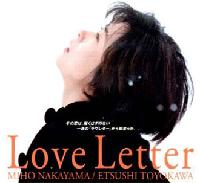記事入力 : 2006/02/01 20:11
【記者が行く】映画『Love Letter』の街 小樽
岩井俊二監督の映画『Love Letter』は韓国の映画ファンに最も愛された日本映画だ。小樽を舞台に美しい恋物語を描いたこの映画は韓国の映画ファンの間に一種のカルト現象までもたらした。「お元気ですか」という台詞は韓国で流行語にもなった。そんな映画の舞台、小樽を朝鮮日報のイ・ドンジン映画担当記者が訪れた。
こんな雪は初めてだった。札幌を発った夜汽車が小樽に向けて走る間、目には一面の雪が映っていた。汽笛を鳴らしながら雪の世界へと吸い込まれる汽車が消失点に向かって線路の上を寂しく走る時、レールの左右に出来る吹雪がそれさえも微かに残っていたリアリティーを消した。垂直に降りしきる雪と水平に開かれる雪が湖のように美しく出会う白い夜はぼんやりとしていた。
110年の伝統を誇る旅館に宿泊すると朝8時に女将が部屋に入って来て布団を畳んだ後、ひざまずいてあいさつをする。部屋の真ん中に用意された食事をとり、『Love Letter』の撮影地である小樽市内を歩いた。雪と重なり合い美しい風景を醸し出している運河周辺を散策し、映画に登場した硝子工房の見晴らし台に上がると、ノートに韓国人観光客が残した言葉が多く残されていた。「君と初めての旅行。本当に最高だ。ここに来て良かった」という男性の言葉の下に女性が短く一言。「○○さん、愛してる」。愛の思い出は消えても、愛の跡は不滅だ。
午前の小樽郵便局は慌ただしかった。郵便局前の十字路で手紙を出した後、自転車に乗って去ろうとした藤井樹(女)は自分の名前を呼ぶ声を聞いて後ろを振り向く。名前を呼んだのは山の遭難事故で失った恋人、藤井樹(男)を忘れることができず、彼が中学時代に住んでいたこの場所に訪れていた博子だった。すれ違ったばかりの人が同級生だった樹(男)に対する思い出を自分に手紙で知らせてくれた同名異人の樹(女)ではないかと思ったからだ。しかし、人波の中で二人は互いを見つけることができなかった。
『Love Letter』ではこうした幻想と現実の間の曖昧な場面が多かった。雪に覆われた小樽で撮られた映画はそれでも良かった。冬は幻想的な季節だからだ。
車に乗って東南の方向へ10分余り行くと朝里中学校が見えてくる。劇中2人の樹が通った学校だ。40代の日本語教師の親切な案内を受け、小さな校舍をじっくりと見学した。撮影場所だったという2年B組に入って樹(男)の椅子に座ると自分の10代の頃と映画の中学生活が次々と重なっていった。正門から出た時、他の教師と出くわすと英語で話すために今まで無口だった案内役の日本語教師が日本語でこう叫んだ。「『Love Letter』の取材で韓国から来た記者なんだ」。
玄関で女子生徒たちに会った。カメラを向けると恥ずかしいと笑いながら逃げ出した。3年生のバスケットボール部員だと言うが思ったよりも背が小さかった。 大人には子どもはいつも幼く見える。しかし、その幼い子どもたちも『Love Letter』のように彼女らなりに真面目な恋の病にかかる。
小樽と札幌の中間あたりにある銭函駅の近くには劇中、樹(女)が住んだとされる家がある。前もって何回も電話をしたが繋がらず、住所だけを頼りにタクシーに乗った。あいにくの吹雪で道に迷い、何とか近くまで辿り着いたが雪のために車を降りて家の前まで200メートルほど歩いた。丘の下の路地の先にあるその家は映画に登場したそのままの姿だった。しかし、いくら呼んでも誰も返事はしなかった。静寂の中に降り積もる牧丹雪の音が聞こえるだけだった。
映画の冒頭で博子が雪の上を走っていた天狗山スキー場は小学生の団体スキー客で賑わっていた。スノーボードを滑る人々に混じってケーブルカールで山に登った。どこまでも雪に覆われた市街地と海を見下ろそうとすると一年のはじめでもあり終りでもある冬が「環」の季節である事実を悟る。境界を無くして世の中を沈黙させる夢幻的な雪の中では、はじめも終りも結局は互いにしっぽを掴んで果てしなく回る時間がループする小さな点に過ぎなかった。
スキー場から下りるケーブルカーに乗っているのは私一人しかいなかった。『Love Letter』は既にこの世を去った一人の男性との恋愛を思い出す二人の女性の思い出を扱った映画だった。ギリシャ神話で時間の神は空の神と地の神の間に生まれた。小樽の冬、空と地の間には白一色の雪が時間を覆っていた。降りしきる雪の中で情熱も懐かしさも夢も現実もすべてが果てしなく感じられた。ケーブルカーがゆっくりと動き出した。再び現実に戻らなければならない時間になった。しばらく雪の中に埋もれて起き上がり、山を仕方なく下りるしかなかった博子のように。