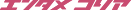記事入力 : 2009/01/01 01:01
安藤忠雄氏「建築は秩序や礼儀を知ってこそできるもの」
素晴らしい建築物が多く集まる京畿道坡州市の「ヘイリー芸術の村」や、ソウルの清潭洞を歩いていると、塗装を施していない、灰色のコンクリートがむき出しになった建物が多い。数年前から流行している「打放しコンクリート」という建築技法だ。日本の建築家・安藤忠雄氏(67)=写真=は、この建築技法を一つの「芸術」としてグレードアップさせた巨匠だ。アジアを代表する建築家として知られる安藤氏を取材するために、記者は昨年11月1日、大阪にある彼のアトリエに訪ねた。
大阪市北区の閑静な住宅街にある安藤氏の事務所。彼のトレードマークである打放しコンクリートの外壁が、大きな看板のように目前にそびえ立つ。入口には看板らしきものはなく、ただ表札が掲げられているだけだった。
「何分かかったって言った? 何分?」事務所に入るや否や、ぶっきらぼうでドライな感じの声が本の山の向こうから聞こえてきた。あいさつの代わりに聞こえてきた安藤氏の第一声。安藤氏の事務所は数万冊もの本で埋め尽くされていた。出入り口の横の、安藤氏の机が置かれているところは、4階まで吹き抜けになっている。
インタビューには事務所の新人スタッフと、古参のスタッフが一人ずつ同席した。「スタッフの前ではうそをつけないでしょう。それに、わたしがスタッフに対して“わたしがどんな人間か”と言ったところで意味はない。皆頭が悪いから、すぐに忘れられてしまうのがオチだ」。安藤氏は笑いを交えながらこう切り出したが、スタッフたちは微動だにせず、話を静かに聞いてメモを取っていた。安藤氏はスタッフが怠けないよう、「時々殴ることもある」という(安藤氏は「20年前に殴ったことがある」と話したが、あるスタッフは「最近も殴られた」と耳打ちした)。また、図面をメモするテストも課すという。安藤氏の建築物からにじみ出る、厳格ともいえる節制ぶりと緊張感が、スタッフの教育にも反映されているというわけだ。
事務所は「デジタル」とは程遠いものだった。インターネットに接続したパソコンは1台あるのみ。事務所のメールアドレスも一つだけだ。日本国内での書類のやり取りはすべて郵便を利用する。「建築が既成のデータの取捨選択になってしまうのを防ぐためだ」と安藤氏は話す。
「建築は礼儀です。家の構造には玄関、居間、自分の部屋という順序があるように、建築にも秩序というものがあります。その秩序や礼儀というものを知ってこそ、建築ができるのです。なので、スタッフや学生たちには常に基本的なことを守るように言います」。安藤氏は「母方の祖母が教えてくださった勤勉な態度と礼儀作法が、わたしの建築の根幹だ」と話した。双子の兄弟として生まれた安藤氏は、幼いときから母方の祖母の家で育てられ、名前も母方の祖母の姓に変えられた。なお、双子の弟は商業施設のコーディネーターとして活躍している北山孝雄氏だ。
元プロボクサーという経歴は、安藤氏について説明する際に必ず付いて回る。安藤氏は「韓国のメディアの報道を見ていると、“建築はボクシングだ”というわたしの言葉を引用し、まるで建築がケンカのようなものだというニュアンスを漂わせているが、それは間違いだ」と指摘した。「建物を建てるとき、お客さんとどこまでも話し合い、追求していく中で刺激を受けるものだ。“外部から常に刺激を受ける”という意味で、建築はボクシングと似ていると言っているのだ。このことを必ず記事に書いてほしい」と安藤氏は求めた。
安藤氏はさらに、「建築は愛情だ」と強調した。「生きているものに対する愛着がなければ、優れた建築家にはなれない」というわけだ。自らを「人情にあふれた変わり者」という安藤氏はある日、事務所に迷い込んできた子犬に、自分が尊敬するル・コルビュジエ(フランスの建築家)にあやかった名前を付け、大切に飼い続けたという。そんなエピソードもまた、ぶっきらぼうな表情の中に隠された彼の温かい心を感じることができるものだ。
インタビューが終わるころ、安藤氏は「建築は終わりなき旅のようなものだ」と言い、「俳句の父」といわれる松尾芭蕉の「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」という一句を紹介した。
「建築」という長い放浪の旅を続ける大建築家の夢と挑戦は、いまだに荒野をさまよい続けているようだ。
大阪=キム・ミリ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 「東郷平八郎が李舜臣を称賛」 全て作り話だった(上) 2025/8/14 11:35
- 「東郷平八郎が李舜臣を称賛」 全て作り話だった(下) 2025/8/14 11:00
- 「憲法裁は尹大統領罷免の過程で明白な過ちを犯した」 韓国政治学会の重鎮が指摘 2025/8/11 14:15
- 『金大中 亡命日記』初出版 1972年10月維新前後に米・日で記録した223ページ 2025/8/3 11:25
- スポーツに関心ない人にもこの世界の美しさを…山際淳司著『スローカーブを、もう一球』 2025/7/27 07:00